
"世の中を良くする"という
思いを原動力に、
MRAで、MRAとともに
成長を。
01
技術で、社会の課題を解決し、未来を創る。
まず、私たちエム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社(以下、MRA)は、その特長である「技術に強い」ことを、三菱総合研究所(以下、MRI)グループにおいて発揮していきたいと考えています。一つのグループとして、両社が「社会課題の解決」を目指していることは同じです。いま社会では「財務価値」だけでなく「非財務価値」が重視されており、MRAもこれを経営上の重要指標と捉えて社会課題を解決し、より良い未来社会づくりに貢献します。
MRIグループでは、「価値創造プロセス」(VCP: Value Creation Process)の実践を進めています。これは、社会課題を起点に、研究成果の発信や政策提言、そして調査分析・事業構想、さらには実社会への実装に向けた研究結果の実証、最終的には実際の事業化までを連接して社会変革を実現する一連のプロセスです。MRAはその中で、分析・解析などの技術を活かし、調査分析・事業構想、研究結果の実証を中心にしっかり貢献していきます。
私たちのお客様は約半数が官公庁で、MRIから受託する案件でも、元々のクライアントの多くは官公庁です。このため、我が国の喫緊の課題解決のため、世の中の制度の変更や、新たな仕組み作りに取り組んでいます。具体的には、ある制度を策定する場面を事例にすると、「本当に効果が出るのか、安全なのか」といったことを、シミュレーションなどを用いて確認・検証するといった仕事です。確かなシミュレーションには、しっかりとした技術が必要であり、それをMRAが担っていく。そんな「技術の強さ」を前面に出していきたいです。
社会の様々な分野で貢献していきたいと考えています。例えば、「防災・安全」では、自然災害が生活・産業に与える影響などをシミュレーションし、どの様な準備をすれば被害を軽減できるのか、産業面ではBCP(事業継続計画)の策定とその実効性の確認などが重要だと考えています。また、「循環社会」については、環境負荷を下げていくためのエネルギービジョンを検討し、省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用を支援する事業を進めています。その他にも、都市施設、交通・電力網、上下水道といったハードインフラや、医療・介護、脱炭素、社会安全(犯罪・子供安全対策など)といったソフトインフラなど、幅広い分野で豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。


02
若い時から、前線で。そこから育つMRAの人材。
若い年齢層が比較的多いからかMRAには「自由闊達さ」を感じています。何かをやってみようと思ったときに素早く着手できる、そんな風土があると考えています。プロジェクトを受託する際に、社員たちが素直に「すごく興味があって、やりたいんです」と言ってくるのが印象的です。プロジェクトのリーダーに若い社員が就いていることも珍しくなく、活気を感じます。世の中を変えるには発想の豊かさが重要ですので、会社としても「画期的で、斬新なアイデア」によって、いろいろな事に積極的に取り組みたいと思っています。
そして、それを実現するには、技術力と行動力を併せ持つ「人材」が大事です。MRAには人を育成するための、充実した研修や社会人大学院通学などへの支援制度があります。社員にはこれを利用してもらいつつ、OJT(On-the-Job Training、オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を中心とした実務の中での成長を期待しています。下積み時代を社内に閉じこもって過ごすのではなく、若いうちからお客様のもとへ伺い、直接対峙して一緒に仕事を進める。その中で、プロジェクトの本当の目的を理解し、与えられた役割の意義を考え、視野を広く持って自分がいるべき所を見定めようとする。そんな姿勢で仕事を進めることが、力をつけていくための一番のポイントになるでしょう。厳しいところはあるかもしれませんが、それに代えがたい面白さがあるはずです。
MRAではMRIグループとして取り組む仕事の基礎的な部分も多く担っているため、何かを調べたり、まとめたりする地味な業務も多くあります。コンサルタントやリサーチャーになる上では、若いうちに基礎的なことをしっかりとやることが、すごく重要だと私は思っています。MRAでしっかり仕事に取組み、自分の中に確かな基盤を築いて力がつけば、きっと世の中に名前が轟くような人にもなれるでしょう。私はなかなかいい会社だと思っています。
働き方改革にも取り組んでおり、フレックスタイムや裁量労働に加え、リモートワークの活用も進んでいます。在宅とリモートワークを組み合わせた、MRAならではのハイブリット勤務を追求しているところです。社員一人一人が、自らに合った働き方をうまく使い分けることで、仕事と家庭を両立させ、ワークライフバランスを確保する。そのような姿が、望ましいと思っています。

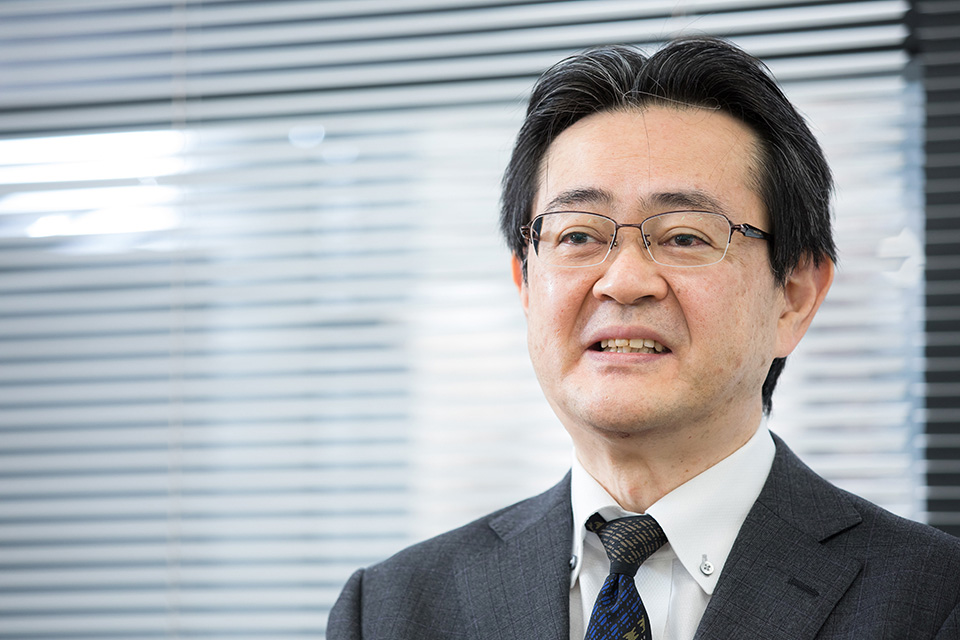
03
"自分"を活かして、夢を実現したい人のエントリーを。
MRAでは、未来社会の実現に向けた検討や、将来のあるべき姿を考察する機会が多く、夢の実現に取り組むことができる会社です。だから、目標を持って入社してきて欲しい。まずは学生時代に学んだ知識や今後MRAで身に付ける技術などを「何に活かしたいのか」、そして「何をしていきたいのか」を明確にし、エントリーしてもらいたいと思っています。
求めている人材というと、誤解を恐れずに言えば「尖っている人」でしょうか。オールマイティである必要はなく「特定の技術に強い、特定の分野に強い興味を持っている」といった人に魅力を感じます。MRAではチームプレーで働くことが多く、一人で全部できる必要はありません。技術に強い人、プロジェクトをコントロールできる人、お客様と上手くコミュニケーションできる人などが集まり、お互いの良いところを組み合わせて上手くプロジェクトを進めていきます。ですので、何か一つ「私はこれに自信がある、これで世の中を変えたい、良くしたい」と思えるようなことがある方に入社していただきたい。そうすると、社内に活気が出ますし、いろいろな意味で広がりが生まれると思います。
だからと言って、シンクタンクや研究所といった組織で働くには「大学ですごく勉強しておかなければならない」「ものすごい能力がなければいけない」と思わないで欲しいです。大学で4年、修士課程までで6年という勉強期間を、社会に出てから働く数十年という期間と比べたとき、どちらが本当の力になるでしょう。入社してからの方が、ずっと大きな経験や学びがあるはずです。MRAへ入社して日々勉強し、自分で興味を持ったものに取り組み、困難を乗り越えながら力をつけていくことが重要だと私は思っています。現時点で、高い専門性がないからダメなんじゃないかと考えず、「世の中を良くしたい、こういう社会課題を解決したい」といった強い思いがある人には、ぜひ入社していただきたい。MRAで、MRAとともに成長していきましょう。「will」がある人に来ていただいて、一緒に仕事ができるという形が、一番ハッピーだと思っています。

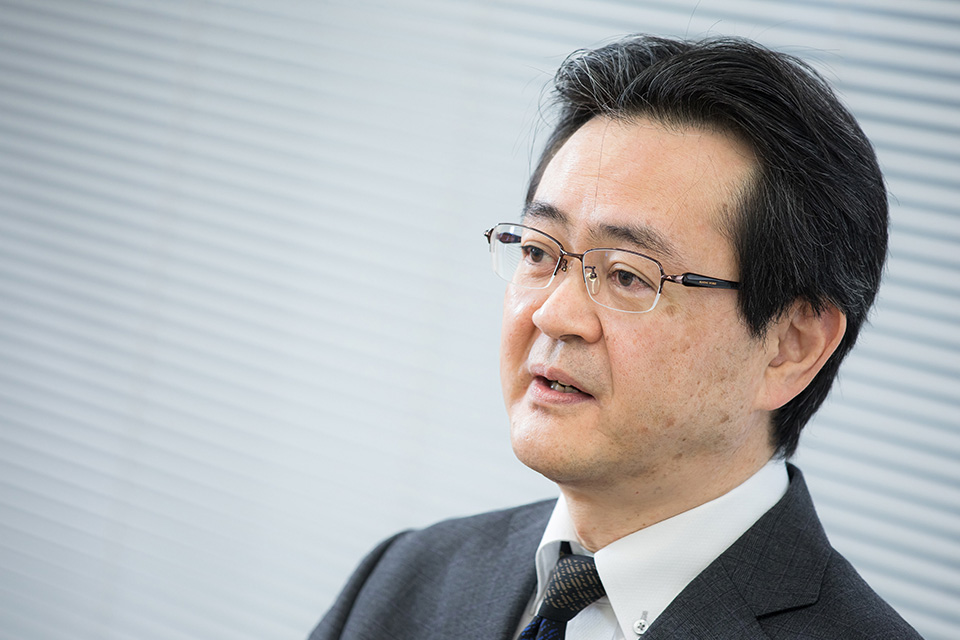
Profile
- 1965
- 千葉県市川市生まれ
- 1991
- 大学院:理工学研究科
建設工学専攻 都市計画専修 修了 - 1991
- 三菱総合研究所(MRI)入社
- 2016
- 次世代インフラ事業本部長
- 2019
- コーポレート部門統括室長
- 2020
- MRA社長に就任
