
あなたの専門性や技術力を、社会のために。
発揮するも、成長するも、
MRAならきっとできる。
01
解析力に秀でた技術系シンクタンクとして、より存在感を高めたい
「シンクタンク」とは、より良い未来をつくるため、社会の幅広い分野で調査・研究に取り組み、課題解決へ向けた立案・提言を行う組織です。アメリカなどでは社会の『公器』として、民主主義における公共政策の立案を担う一つのシステムであると認識されています。公共政策において、まずは政治があり、行政があり、第三極としてシンクタンクがあるわけです。我が国の社会課題解決をするための期待に応えたいと、三菱総研グループだけでなく、日本のシンクタンク業界全体が考えていると思います。
三菱総研グループでは社会変革を先駆けることを経営理念に掲げ、社会課題を起点とした調査研究・分析から、その成果の発信や提言はもちろん、事業の構想、社会実装に向けた実証、そして事業化まで、一連のプロセスを精力的に推進してきました。グループの一員である私たちエム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社(以下、MRA)は、高度な専門性や技術力で存在感を発揮し、独自の成果を上げています。
私たちは、交通インフラ、医療介護、防災など公共的なテーマに関心があり、我が国の喫緊の課題解決のため、制度設計や、新たな仕組み作りに取り組んでいます。そのため、お客様は約半数が官公庁で、三菱総合研究所(以下、MRI)から受託する案件でも、多くが官公庁となります。具体的には、ある制度を策定する場面を事例にすると、「本当に効果が出るのか、安全なのか」といったことを、シミュレーションなどを用いて解析し、確認・検証するといった仕事です。確かなシミュレーションには、しっかりとした技術が必要であり、それをMRAが「技術の強さ」で担っていくことで強みを発揮してまいります。都市・インフラ・モビリティ、医療・介護、防災、エネルギー・循環・サステナビリティ等、社会のさまざまな分野で、豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。
MRAは、MRIのシステム開発・解析事業を担う会社として発足し、名称や役割を変えながら2024年に創業40周年を迎えました。節目となる50周年に向けて長期ビジョンを策定、強みを一層追求し、「より解析力に秀でた技術系シンクタンクを目指す」という方向性を定めました。今期はこれをさらに具体化する計画であり、10年後の会社の在り方や売上規模などをトップダウンではなく社員自ら議論し、目指すべき姿を描き出してもらいたいと考えています。


02
専門性・技術力のある「人材」が資産。さらなる成長を、会社が後押し
社長就任前から、MRAの専門性や技術力の高さを感じていましたが、社長就任後、その認識は、一層強くなっています。世の中の事象が複雑に絡み合い、関係する事柄が増え、さまざまな分野での知見が求められてきた中で、シンクタンクもより広範な専門性を身に付けることが求められてきています。そうした潮流においても、MRAには専門性へのこだわりを強くもつ社員が多いと感じます。
高い専門性と技術力を有すことがMRAの特長や強みであり、存在価値です。そしてシンクタンクという業種において、専門性や技術力は人に依るところが大きいことから、当社の資産は「人材」だといえます。このため、社員個々人のパフォーマンスをいかにして上げるかが重要であり、「一人ひとりの専門性」をより発揮してもらうために『柔軟な働き方』を推進しています。仕事の内容に対して最適な職場環境というものが、きっと一人ひとりにあるはずで、これを仕組みとして会社が提供できるよう取り組んでいます。リモートワーク環境の整備はもちろん、それを活かした地方移住制度もあり、ご家庭の事情で地方に暮らさなければならない社員に、辞めることなく引き続き活躍してもらっています。フレックスタイムや裁量労働といった働き方ができ、社員一人ひとりが、自らに合った制度を利用することにより、仕事と家庭を両立させ、ワークライフバランスを確保できるようにしています。
そして、専門性や技術力をさらに高めてもらうことも重要です。仕事を通じて、あるいは自主的な学びや研究において、成長する機会を提供したいと考えています。三菱総研グループ社員(各分野の専門家)と仕事をすることでも成長の機会が得られることは当然ですが、業務で何か新しい試みをするならば多くの場合、有識者らとの会合などが必要になります。そのような機会に有識者の方と議論し、最先端の技術を吸収することで、当社の社員自身のスキルアップを期待しています。
自主的な学びや研究においては、充実した研修や社会人大学院への通学支援といった制度があるだけでなく、より高みを目指し、各社員が自らの発想に基づいておこなう自主研究の支援もしています。例えば、就業時間のうち一定の割合を自身の興味ある研究のために使ってよい制度があります。さらには、最先端の技術を外部研修等で積極的に吸収することも奨励しており、社員がさまざまな学会への参加、講演会での発表、論文投稿する活動も推奨しています。MRAにはアカデミアに近い環境があります。

03
フラットな雰囲気でリーダーを支えながら、推進していくプロジェクト
MRAには、若い社員が早くから活躍し経験を積める機会があります。プロジェクトマネージャーに抜擢される年齢も5歳ほどでしょうか、MRIに比べて少し早い印象があります。経験が浅いうちに抜擢されて、いくつかの苦労をすることがあるかもしれませんが、それも貴重な経験ではないでしょうか。何より、プロジェクトのメンバーが年齢の上下に関係なくリーダーを支える風土のようなものがあります。別の言い方をすれば、人間関係がとてもフラットです。MRAは決して規模の大きな会社ではありません。しかし、それが人と人とを近しくしている。組織階層でいえば、社員がいて、組織管理者としてチームリーダー、部長がおり、その上が社長ですので階層が3つ、4つしかない。そのため私も普段、社員といろいろな会話をしますし、個々のプロジェクトの中身にも目を向けています。普段の職場の様子を見ていると、ベテランから若手まで社員皆がオープンな雰囲気で、議論を純粋に楽しんでいます。これは、常に新しい課題と向き合うという、私たちの事業特性によるところが大きいと思います。解決策や答えはまだ誰も知らないわけで、それを皆で探求していくとき、上の人が下の人に何かを教えるという形になりにくいからだと考えます。技術や専門分野を語る上で年齢の上下はあまり関係がなく、皆が自由闊達な姿勢でいられるようです。

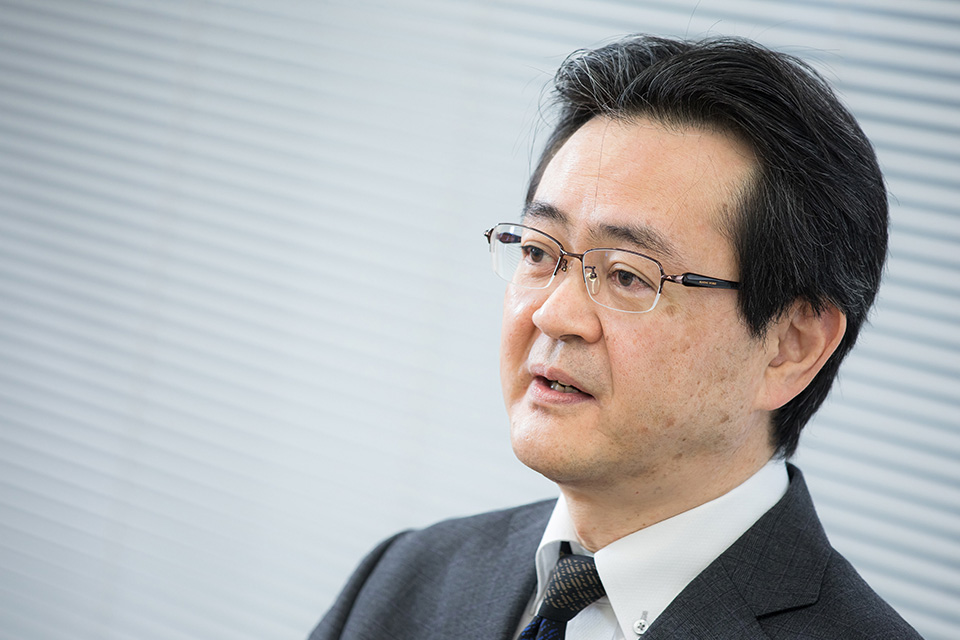
04
好奇心や熱意があれば、きっとMRAで自身の能力を社会に役立てられる
求める人材は大きく3つ。1つ目は、好奇心旺盛な人です。「何か新しいことを知ろう」「なぜこうなっているのだろう」と原因を探求する姿勢に溢れ、それを楽しめるモチベーションがある人たちが、この職種に合っていると考えるからです。2つ目は、お話してきましたように、自身の専門性にこだわりたいと思っている人です。好奇心と専門性の2つを掛け算できれば、当社で活躍していただける期待がより膨らみます。そして3つ目は、伝える能力が高い人です。研究成果を分かりやすくお客様や社会に伝えていかなければ、私たちの仕事の価値は顕在化されません。よって、この3点の資質をもつ人材が、やはり成果を上げています。ただ、入社を希望されるにあたり重要なのは始めの2点で、3点目は入社後の研修等で身に付けることができます。成長するための確かな機会やサポートが、MRAにはあるとお考えください。
当社を志望してくださる皆さんは、勉強してきたことを活かして「何か社会に貢献したい」という熱意をお持ちです。また多くの方が「自分はこんな分析ができる」「こういったテーマに携わりたい」と言われます。私たちは、それを具体的な業務や目指すべき成果として、より明確化してあげたい。そして活躍の場を提供していきたい。皆さんが夢を実現できる会社であり続けていく所存です。

Profile
- 1966
- 東京都墨田区生まれ
- 1991
- 大学院:工学研究科
構造工学専攻 修了 - 1991
- 三菱総合研究所(MRI)入社
- 2016
- 科学・安全事業本部長
- 2019
- シンクタンク部門統括室長
- 2022
- ポリシー・コンサルティング部門長 執行役員
- 2024
- MRA社長に就任
